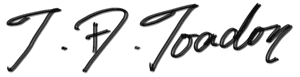>>TOP
>>TOP
 >>TOP
>>TOP
[MENU]
[HFLAとは?]
[とーどん導師]
誰かが言った。「蛙あれ!」と。そこに蛙がいた。
これは、あの偉大な作曲家であり、インベーダーゲームの大家でありながら、常に民衆の立場でパチンコをやりつづけた(そして決してパチスロはやらなかった)私の祖母の言葉です。彼女が山左のカエルパチスロ、パルサーシリーズを知らなかったことは、ある意味家計にとって助かる結果ではありましたが、彼女の幸せとして見た場合、果たしてどうでしょうか。
パチスロの面白さを知らなかったことは不幸なのか、それとも面白さを知らずに死んだことが幸せなのか。本人の主観の問題として見ても、極めて回答の難しい問であるといえます。
幸せとは何でしょう?極めて単純化して考えれば、これは、欲求が充足されている状態のことと言っていいでしょう。人のために犠牲になることが幸せな人であっても、もちろん他の蛙のために犠牲になる蛙であっても、本質は、その人にとっての価値体系の中でより高いものを選択する、そういった本人の欲求の満足であることに変わりはありません。
しかし、一方で欲求の実現には様々な制約がかかります。ステーキを腹いっぱい喰いたい、という、まあどうということもない欲求であっても、金銭上の制約条件があります。要するに、諦めて毎日ほどほどの食生活を送るか、良い肉を1kgでも買い込んで、残りの給料日までの日々をご飯に塩をかけて過ごすか、豚肉のステーキに変更するか、肉代を稼ぐためにアルバイトするか、一定の制約条件のなかで自己の欲求に沿った最大値を見つけるべく、様々な選択肢のなかから一つを選びとらなければいけません。
選択肢の一覧から決断を行う場合、自分の欲求の充足のあらゆる面について検討を行い、各要素に自分の好みに応じたウェイト付をして、総合ポイントを比較し、高いものを選択するわけですが、この計算は容易ではありません。牛肉と豚肉との美味さをポイント化し、価格と量とのバランスを踏まえ、また、一点豪華主義と日常生活の安定との人生観の問題を考慮し、最近の腹の出ぐあいとか、狂牛病騒ぎやアメリカの圧力、ひいては日米関係への影響なんかも想定したときに、最適な選択が何か、なんてことがわかるわけがないのです。前提となるウェイト付けだって、基礎となる情報に不足や誤りがあれば、結果は全然違うものになります。隣のスーパーでは実は牛肉半額セールをやっていた、なんて情報を見落としていた場合を考えてみてください。
それに、そもそも選択肢が網羅されているかどうかも分かりません。最適解は、実は羊肉でジンギスカン、かもしれません。
結局のところ、各種の制約条件の中で最大限の幸福(欲求の実現)を求める結果、人は選択の困難さに伴う“悩み”と、選択が情報不足等により誤ったことに伴う“後悔”を抱え、選択を精緻に行おうとすればするほど、幸せになる努力をすればするほど、多くの苦悩を抱えるという、矛盾した効果が現れるわけです。
これを「幸福志向 - 不幸量比例の法則」として
選択の最適化に関する努力量 = 選択肢の数 × 選択肢評価のための関連情報量 =判断に係る苦悩の量
のように定式化し、それがためかどうか、もともと所属もしていなかった学会から無視されつづけた稀代の浪費家エコロジストといえば、あの3丁目の早田さんですけれども、あ、早田さんをご存知ない?それは残念です。
このような法則が厳然としてあるにもかかわらず、複雑な情報処理を行うことができる人間の脳は、一瞬のうちに様々な選択肢を準備してしまいます。ひるがえって蛙はどうでしょう。なぜ突然蛙なのか、そういった疑問は別としてください。とりあえず。
蛙の目というのは非常に優秀な器官ではありますが、そこから受け取る像について、蛙の脳が行う情報処理は極めて単純です。インプットデータの中に小さくて動くものがあったとします。蛙は自動的にそれを食べ物と判断します。これは実際に映っているものが不規則に舞い落ちる枯葉であろうが、誰かが糸でつるしてぶらぶらさせている小石であろうが、食べられようが食べられまいが関係なく、ということです。
逆に、大きな動くものが映った場合はどうでしょう。これはもう自動的に避けるべき敵、と判断します。そこで動いているものが何か、ということは全く関係がありません。
一見、これは非常に効率の悪いシステムのように思われるかもしれません。蛙は、食べ物でもないような小石を飲み込んで死んでしまったり、うっかりすれば、同じ仲間を飲んでしまう可能性がある一方、すぐ目の前に動かない虫がいたとしても食べ物があることがわからず、餓死してしまったりするわけですから。しかし、蛙の選んだシステムは、この単純な反応システムだったことになります。判断のための材料を増やし、外界を詳細に分析して、自分にとっての要否を決定する道は、そうしたシステム構築にかかる労力およびそういったシステム運営を行ううえで取られるリソースが膨大になることから、結果的にごく単純な条件のみを材料にして判断する危険の方が少ないと判断され、捨てられたのだと思われます。
蛙は不幸でしょうか。かの有名な、独白する蛙ごびらっふが述べているように、
「おれの単簡な脳の組織は。言わば即ち天である。」(草野心平「定本蛙」)
自然を分析・解釈することなく、あるものをあるようにないものはないものとして生きることは、すなわち自然そのもの(=天)である。極めて含蓄のある言葉でありましょう。
古代の人々は、こうした自然の中に生きる蛙の姿を信仰の対象にしていました。エジプトでは世界そのものの創造に係る神が蛙を形どっていましたし、旧約聖書における神の警告は、蛙の大発生でしたし、映画マグノリアは蛙の雨でしたし。最後のは意味が違いますが。
「原始かえるは太陽だった」
これは、当HFLAの創設者であり、生涯女性の地位向上に尽力した封建主義者である平塚らんでぶー、イタリア人とのハーフですけれども、すなわち、蛙=太陽=神の三位一体論を提唱していたわけですが、これこそが、我がHFLAの基本認識ということになります。
環境が与える刺激への対応を出来るだけ単純化して、欲求への対処の方法を画一化することにより、徐々に欲求そのものが落ち着いてきます。この反応の画一化は、実用新案出願中の欲求−反応定式チェックシートを用いて事前に最適な反応を選択することにより行い、他の選択肢について、大胆に情報への対処を行い、長い間絶滅を避けつづけた偉大な蛙の姿を想像しながら排除する、この繰り返しこそが、苦悩からの開放であり、また、幸福の実現なのです。
選択肢の渦の中で出口がなくなりそうになったとき、蛙の姿、HFLAではこれを「瞼のケロリ」と呼びますが、このケロリを思い起こすことで、ケロリと選択肢が消えます。いわば極楽往生を願ってただ一心に阿弥陀如来に念仏を唱える浄土真宗と似たイメージかもしれません。また、無念無想の禅の心にも繋がるでしょう。選択肢消去の効果であれこれと悩む必要がなくなり、生活の中に平安が訪れます。
我々HFLAのメンバーは、この幸福、平安をできる限り広げていきたい、この素晴らしさを、蛙の偉大さを伝えていきたい、そうした熱意にあふれた、あふれすぎて煮えたぎるような、灼熱の太陽のような、とにかく、熱心な者と、そうでもない者が集まっています。設立趣意にご賛同いただける方はどなたでも入会を受付けております。さあ、貴方もいっしょにケロリとしましょう!!